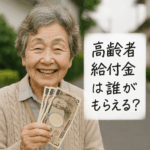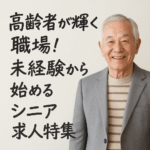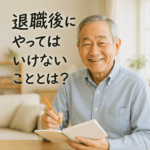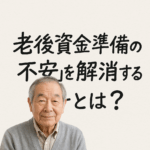高齢者雇用継続給付金とは?年金との違い・申請方法・メリットとデメリットを徹底解説

高齢者雇用継続給付金と年金の違いを理解していますか?この記事では、申請条件・支給額の目安・申請手続きの流れを徹底解説し、損をしないためのポイントや体験談を紹介します。

高齢者雇用継続給付金の基礎知識
Contents
- 1 高齢者雇用継続給付金とは?
- 2 65歳以上の高齢者を対象とした制度
- 3 高年齢者雇用継続給付金廃止の背景と影響
- 4 支給対象となる条件と必要書類
- 5 給付金の計算方法と支給額
- 6 支給期間と申請手続きの流れ
- 7 年金と高齢者雇用継続給付金の違い
- 8 給付金が年金に与える影響
- 9 年金がカットされる場合の注意点
- 10 給付金の受給による可能性のあるトラブル
- 11 企業側の雇用管理への影響
- 12 高齢者の再就職時の留意点
- 13 2025年以降の高齢者雇用への影響
- 14 今後の制度改正予定と解説
- 15 高齢者雇用を支援する企業の役割
- 16 給付金の効果的な活用法
- 17 必要な書類・手続きの早見表
- 18 高齢者雇用継続給付金と他の支援制度の比較
- 19 高齢者雇用継続給付金とライフプラン設計
- 20 給付金申請でよくある失敗と回避方法
- 21 他の世代・家族への影響(配偶者や子ども世代への波及効果)
- 22 海外と日本の高齢者雇用支援制度の比較
- 23 給付金を受けながらできる新しい働き方
- 24 給付金をもらうための会社との上手なコミュニケーション術
- 25 数字で見る高齢者雇用の現状と将来予測
高齢者雇用継続給付金とは?
「高齢者雇用継続給付金」とは、定年後も引き続き働くシニア世代をサポートするために設けられた制度です。
多くの人は60歳で定年を迎えますが、近年では「健康だからまだまだ働きたい」「生活費を補うために収入を確保したい」という理由から、定年後も働き続ける方が増えています。
しかし、60歳以降は給与が大幅に下がるケースも珍しくありません。
役職定年で役職が外れたり、再雇用契約に切り替わったりすることで、給料が現役時代の6割程度になることもあります。
そこで、国は「働く意欲を削がないため」に給料が下がった人に対して一定の補填を行う仕組みとして、この給付金制度を用意しています。
つまり、単なる生活補助ではなく「働き続ける高齢者を応援する仕組み」であり、雇用を延長する会社にとっても労働力を確保できるという利点があります。
65歳以上の高齢者を対象とした制度
高齢者雇用継続給付金の対象は、原則として60歳から65歳未満の方です。
特に、雇用保険に継続して加入しながら働いている人が支給対象になります。
65歳を超えると原則として支給は終了しますが、制度の経過措置によって対象年齢や条件が変化しているため、現在の年齢や就業状況によっては例外的に受けられる場合もあります。
この「60歳から65歳まで」という年齢制限は、まさに「年金受給が本格化するまでの繋ぎ役」としての性質を示しています。
たとえば、60歳から65歳までは「給付金+給与+一部年金」で生活を支え、65歳以降は「年金+給与(在職老齢年金制度を調整)」という流れに移行していくのが一般的です。
高年齢者雇用継続給付金廃止の背景と影響
一方で、この制度は近年「廃止の方向」で議論が進められています。
理由のひとつは、少子高齢化の影響で「年金や雇用を巡る財源」が厳しくなっていることです。
また、年金と給付金の両方を支給するのは「二重の公的支援」になるのではないかという批判もありました。
さらに、現在では「70歳までの就業確保措置」が努力義務化されており、高齢者の就業機会が広がっています。
「給付金に頼らずとも、高齢者は働きながら収入を得られる環境が整いつつある」というのが国の考え方です。
ただし、制度がなくなることで「給与が減少しても補填がなくなる」ため、生活に不安を抱える人も出てくるでしょう。
廃止が段階的に進められている今、対象となる人は早めに制度を確認し、受給できる間にきちんと申請しておくことが重要です。
高齢者雇用継続給付金のサポート内容
支給対象となる条件と必要書類
給付金を受け取るためにはいくつかの条件を満たす必要があります。
主な条件は以下の通りです。
雇用保険に加入していること
60歳以降も継続して働いていること
賃金が60歳到達時の75%未満に低下していること
特に「75%未満」という基準がポイントで、現役時代の給与とほぼ同額を得ている人は対象外となります。
収入が減少した人ほど支給対象になりやすい仕組みです。
申請には以下のような書類が必要です。
会社が発行する雇用証明書
賃金台帳や給与明細
本人確認書類(マイナンバーカードなど)
ハローワークが指定する申請用紙
手続きは基本的にハローワークを通じて行いますが、会社の人事担当がサポートしてくれる場合も多いため、まずは職場に確認するとスムーズです。
給付金の計算方法と支給額
給付金の金額は、「60歳時点の賃金」と「現在の賃金」の差によって算出されます。
大きく収入が下がった人ほど支給額も増える仕組みで、「賃金が下がった分の一部を国が補填してくれる」イメージです。
たとえば、60歳時点で月額30万円だった給与が、再雇用で20万円に下がった場合、この差額の一部を給付金として受け取れます。
実際の金額は賃金日額や支給率によって異なりますが、月に数万円程度の支給を受けられるケースもあります。
ただし「上限額」「下限額」が定められているため、人によって受け取れる額は異なります。
また、賃金の変動がある場合はその都度計算が見直されるため、支給額も変化する点に注意が必要です。
支給期間と申請手続きの流れ
支給期間は、原則として60歳から65歳までの5年間です。
ただし、60歳からすぐに支給が始まるわけではなく、条件を満たしたタイミングからの支給となります。
申請の流れは以下の通りです。
勤務先に申請の意思を伝える
会社が証明書を発行
必要書類を揃えてハローワークへ提出
初回申請後、定期的に更新手続きを行う
給付は「2か月ごと」に行われるのが一般的で、そのたびに勤務状況や給与額を確認して申請する必要があります。
手続きを怠ると支給が止まってしまうため、忘れずに更新することが大切です。
年金との違いを理解する
年金と高齢者雇用継続給付金の違い
「年金と給付金はどちらも老後のお金」というイメージがありますが、性質はまったく異なります。
年金は「保険料を長年納めてきた人に支給される老後の生活保障」であり、給付金は「雇用を継続する高齢者への一時的な支援」です。
つまり、年金は国民全員が加入している公的保険制度で、ほぼ必ず支給されるもの。
一方で給付金は、条件を満たした人だけが申請して受け取れる限定的な制度です。
両者を混同してしまうと「年金がもらえないのでは?」と不安になる方もいますが、基本的に給付金を受けても年金受給資格が失われることはありません。
給付金が年金に与える影響
「給付金をもらうと年金が減るのでは?」と心配する方も多いですが、基本的には両方を同時に受け取ることが可能です。
ただし注意が必要なのは「在職老齢年金制度」です。
これは、年金を受給しながら働いて給与を得ている場合、収入が一定額を超えると年金が一部カットされる仕組みです。
たとえば、給与と年金の合計が月47万円を超えると調整が入る可能性があります。
つまり「給付金自体が直接年金を減らすわけではない」が、「働いて収入を得ていることにより年金が減額される場合がある」という点が重要です。
年金がカットされる場合の注意点
在職老齢年金の調整によって年金がカットされるケースは少なくありません。
特に厚生年金に加入して働いている人は影響を受けやすく、収入が多い人ほど年金額が減る可能性があります。
「気づいたら年金が思ったより少なかった」というトラブルを避けるためにも、自分の収入や働き方を早めにシミュレーションしておくことが大切です。
ハローワークや年金事務所では相談窓口が設けられているので、不安があれば積極的に相談してみましょう。
また、年金と給付金を組み合わせることで「60歳から65歳までの収入の空白を補う」ことができるのは大きなメリットです。
正しい知識を持って計画的に働けば、老後の生活資金に余裕を持たせることも可能になります。
高齢者雇用継続給付金のデメリット
給付金の受給による可能性のあるトラブル
高齢者雇用継続給付金は、生活を支える大きな助けになる制度ですが、受給に伴うトラブルも存在します。
代表的なものとして、まず「年金との調整不足による誤解」が挙げられます。
給付金は基本的に年金と併給できますが、在職老齢年金制度の影響で収入が一定額を超えると年金が減額されるケースがあります。
これを知らずに給付金を受給し続けると「予想より年金が少ない」というトラブルにつながりかねません。
また、申請時の書類不備や遅延もトラブルの原因になります。
ハローワークへの申請は2か月ごとに必要で、更新を忘れると支給が一時停止されることもあります。
特に複雑な書類が多いため、初めての方は戸惑いやすく、企業や家族のサポートが欠かせません。
さらに、給付金の制度自体が今後縮小・廃止に向かっているため「せっかく計画を立てていたのに制度がなくなる」というリスクもあります。
利用を検討している場合は「今のうちに受け取れる条件かどうか」を必ず確認しておくことが重要です。
企業側の雇用管理への影響
給付金制度は高齢者本人にとってありがたい仕組みですが、企業にとっては雇用管理上の課題を生み出すこともあります。
たとえば「給付金をもらえる条件に合わせて給与を調整してほしい」という声が従業員から出ると、人事制度に歪みが生じる可能性があります。
また、高齢者を再雇用する際に、本人は給付金を受けられることを前提にしているのに、会社側の制度とマッチせずトラブルになるケースも見られます。
「賃金が60歳時点の75%未満」であることが条件であるため、企業が給与設計を行う際に「下げすぎても労働意欲が下がる」「下げなければ給付金対象外になる」という板挟みの状況になることもあります。
結果として、企業にとっては制度を理解した上で給与体系を工夫し、従業員とのコミュニケーションを十分に取る必要があるのです。
高齢者の再就職時の留意点
給付金を受けられるのは「同じ会社での継続雇用」だけでなく「再就職」でも条件を満たせば可能です。
しかし、転職や再就職の際にはいくつかの注意点があります。
まず、新しい職場で雇用保険に加入していなければ給付金を受けられません。
パートや短時間勤務など、加入条件を満たさない働き方を選ぶと対象外になってしまいます。
また、給与水準が思ったより高い場合「75%未満の基準を満たせない」ため給付金を受けられないケースもあります。
「給付金を受け取ることを前提に再就職を考えていたが、結局対象外だった」という失敗例も少なくありません。
再就職を考える際は、給与・雇用形態・勤務時間を含めて総合的に検討し、給付金の可否を事前に確認することが大切です。
制度改正と今後の見通し
2025年以降の高齢者雇用への影響
2025年は日本にとって「団塊の世代がすべて75歳以上になる」節目の年です。
それに伴い、高齢者の雇用や年金に関する制度は大きな転換期を迎えています。
高齢者雇用継続給付金についても、縮小・廃止の方向性が強まり「2025年以降は新規に支給開始ができない」などの制限が設けられる可能性があります。
この影響で、高齢者の生活設計は「給付金ありき」から「年金と労働収入を組み合わせる」方向へとシフトしていくでしょう。
今後は「65歳以上も働き続けるのが当たり前」という社会の流れが強まり、給付金に依存しない働き方が求められると考えられます。
今後の制度改正予定と解説
厚生労働省は、今後の高齢者雇用制度について「年金・労働・企業支援の一体化」を進める方針を打ち出しています。
高齢者雇用継続給付金が段階的に廃止される代わりに、企業に対する助成金制度や高齢者の職業訓練支援が拡充される可能性が高いです。
例えば、企業が高齢者を雇用した際の「人件費補助」や「健康管理支援」が強化されると予測されています。
また、シニアが新しい職種にチャレンジできるよう「リカレント教育(学び直し)」の仕組みも広がるでしょう。
これにより、制度は「個人に直接支給する給付金」から「企業や社会全体で高齢者を支える仕組み」へと変化していくと考えられます。
高齢者雇用を支援する企業の役割
制度が変化していく中で、企業の役割はますます重要になります。
これまでは「給付金を受けられるかどうか」で労働者の生活を支えていましたが、今後は企業自身が「働きやすい環境を提供する」ことが求められます。
たとえば、柔軟な勤務体系の導入、シニア向けの研修制度、健康管理の徹底などが必要です。
「高齢者が無理なく働ける環境」を整えることで、企業は人材不足の解消につながり、社会全体の活力を維持できます。
給付金が縮小する今こそ、企業は単なる雇用の確保ではなく「高齢者がやりがいを持って働ける職場作り」に力を入れるべきでしょう。
高齢者雇用継続給付金を上手に活用する方法
給付金の効果的な活用法
給付金は単に「収入が減った分を補填するお金」ではなく、将来の生活設計を見直すきっかけにもなります。
たとえば、支給された給付金を生活費に充てるだけでなく「医療費や介護費の備え」「老後の旅行や趣味への投資」に活用する人もいます。
また、支給が期間限定であることを踏まえて「65歳以降の生活設計をどうするか」を考えるのも大切です。
給付金をもらえる間に家計の見直しを行い、貯蓄や年金とのバランスを整えることで、安心して老後を迎えられるでしょう。
必要な書類・手続きの早見表
申請に必要な手続きは複雑に見えますが、早見表を作ると理解しやすくなります。
初回申請時:雇用保険被保険者証、会社の証明書、給与明細、本人確認書類
更新手続き:2か月ごとに賃金証明を提出(給与明細や会社の証明が必要)
提出先:ハローワーク
このように、基本的には「会社とハローワークをつなぐ作業」と理解すれば難しくありません。
ただし、期限を過ぎると支給がストップするため、カレンダーに申請日を記入するなどの工夫が必要です。
高齢者雇用継続給付金と他の支援制度の比較
最後に、給付金と他の支援制度を比較してみましょう。
高齢者雇用継続給付金:給与が減った人への直接支援(60〜65歳まで限定)
在職老齢年金:働きながら年金をもらう仕組み(収入によって減額あり)
高年齢者雇用安定助成金:企業が高齢者を雇用する際の支援(企業向け制度)
再就職支援給付金:失業後に再就職した人を支援する制度
このように制度ごとに「対象者」「支給方法」「期間」が異なります。
複数の制度を組み合わせて利用することで、老後の生活資金をより安定させることが可能です。
高齢者雇用継続給付金に関するその他有益情報
高齢者雇用継続給付金とライフプラン設計
高齢者雇用継続給付金は、単に「給与が減ったときの補填」という意味だけでなく、ライフプラン設計の重要なピースになります。
例えば、60歳で役職定年を迎え給与が大幅に下がったとしても、給付金を上手に活用すれば「年金が本格的に支給される65歳までの5年間」を安定して過ごすことができます。
この期間は、老後資金の積み立てを続けたり、持ち家のローンを完済したり、将来に向けた準備を整える時間でもあります。
給付金を「生活費」として使うのはもちろんですが、それ以外に「医療費や介護費の備え」「趣味や旅行に充てて心の健康を保つ」「子や孫への教育資金のサポート」に充てる方も多いです。
つまり、給付金をどのように使うかで老後生活の質が大きく変わります。
さらに、60歳以降に「働きながら給付金を受け取る」という体験は、ライフプランの見直しのチャンスです。
「65歳以降はどのくらい働くか」「年金と給与をどう組み合わせるか」を具体的に考えるきっかけとなり、将来の安心感に直結します。
給付金申請でよくある失敗と回避方法
給付金の申請では、いくつかの「よくある失敗」が見受けられます。
典型的なのは「必要書類の不備」「申請期限の遅れ」「条件を満たしていないのに申請した」などです。
例えば、ハローワークに提出する書類は2か月ごとに必要ですが、この更新手続きを忘れると給付金が一時的に止まってしまいます。
また、給与明細や賃金証明に誤りがあると、再提出を求められて支給が遅れることもあります。
回避するには、以下の対策が有効です。
初回申請の際に「必要書類のチェックリスト」を作る
給与や勤務日数に変動があったときはすぐに確認する
提出期限をカレンダーに記入してリマインダーを設定する
特に「60歳時点の賃金の75%未満」という条件を勘違いしているケースも多いため、勤務先の人事担当やハローワークに早めに相談するのがベストです。
正しく理解して申請すれば、トラブルを未然に防げます。
他の世代・家族への影響(配偶者や子ども世代への波及効果)
高齢者雇用継続給付金は本人だけでなく、家族にとっても大きな意味を持ちます。
たとえば、夫が給付金を受け取りながら働き続ければ、妻の年金生活に余裕が生まれ、世帯全体の収入が安定します。
また、子ども世代にとっても「親の生活が安定している」という安心感は大きく、仕送りや生活支援の負担を減らすことにつながります。
逆に、親が給付金を受けられず収入が大きく減ると、子ども世代の経済的支援が必要になり、二世帯全体の負担が増す恐れもあります。
さらに、配偶者の扶養制度との兼ね合いも重要です。
夫婦どちらかが扶養に入っている場合、給付金の受給や給与額によって扶養から外れる可能性もあるため、家族全体の社会保険や税金への影響も考慮する必要があります。
つまり、この制度は「本人のためだけでなく、家族全体の生活設計に影響する」ものなのです。
海外と日本の高齢者雇用支援制度の比較
高齢者の雇用支援は、日本だけでなく世界中で課題となっています。
日本の「高齢者雇用継続給付金」は給与補填型の支援ですが、海外では異なるアプローチが取られています。
例えば、ドイツでは「部分年金制度」があり、60歳以降は働きながら部分的に年金を受け取り、生活を安定させる仕組みがあります。
北欧諸国では「労働時間を柔軟に減らせる制度」が整っており、短時間勤務や在宅勤務と組み合わせることで、高齢者が無理なく働けるようになっています。
一方で日本は、給与が大きく下がる再雇用制度に合わせて給付金で補う仕組みを作ってきました。
これは「定年制が根強く残る日本独特の制度」ともいえます。
海外との比較を踏まえると、日本の制度は「財源の問題から縮小傾向にある」ため、今後は海外のように「柔軟な働き方そのものを支援する制度」へ移行する可能性が高いと考えられます。
給付金を受けながらできる新しい働き方
これまで高齢者の働き方といえば「フルタイムで再雇用される」か「パートで軽く働く」という二択が主流でした。
しかし、近年は多様な働き方が広がっています。
給付金を受けながら可能な働き方の一例として、
週3日の短時間勤務で無理なく働く
副業や兼業を行い、複数の収入源を確保する
在宅ワークやオンライン業務を取り入れて体力負担を減らす
といった形が考えられます。
特にデジタル技術の発展によって、在宅でできる仕事は増えています。
シニア向けの研修や職業訓練を受けながら新しい働き方に挑戦し、給付金と組み合わせれば、生活の安定とやりがいの両方を得られるでしょう。
給付金をもらうための会社との上手なコミュニケーション術
高齢者雇用継続給付金を受けるためには、会社の協力が欠かせません。
賃金証明書や雇用契約の確認など、会社が発行する書類が必要になるからです。
しかし「会社にお願いしづらい」「制度を理解していない担当者がいる」といった声もあります。
そんな時に役立つのが「上手なコミュニケーション術」です。
まずは制度を自分で理解してから、必要な書類を具体的に依頼する
「自分の生活を支える制度であること」を丁寧に説明する
担当者が制度に詳しくない場合は、ハローワークの資料を一緒に提示する
このように前向きで協力的な姿勢を見せれば、会社側もスムーズに対応してくれます。
「会社に頼みにくいから…」と躊躇するのではなく、積極的に動くことが、給付金を確実に受け取るためのコツです。
数字で見る高齢者雇用の現状と将来予測
厚生労働省の統計によると、日本の65歳以上の就業率は2023年時点で25%を超えています。
つまり、4人に1人以上の高齢者が何らかの形で働き続けているのです。
高齢者雇用継続給付金の受給者数も年々増加しており、ピーク時には年間数十万人が利用しています。
平均的な支給額は月数万円程度ですが、これは年金に上乗せされる収入として非常に大きな意味を持ちます。
将来的にはさらに多くの高齢者が働き続けると予測され、2030年には「65歳以上の就業率が30%を超える」という試算もあります。
しかし、その一方で財源問題が深刻化し、給付金制度は縮小・廃止される可能性が高いとされています。
数字で見ると、給付金制度は「過渡期」にあり、今のうちに利用できる人は積極的に申請しておくべきだとわかります。
口コミ・体験談集:リアルな声でわかる高齢者雇用継続給付金の実態
60代前半・男性(元会社員/再雇用契約)
「60歳で役職定年を迎えてから、給料が一気に3分の2に減ってしまいました。
正直、このままでは生活が厳しいと思っていたところ、同僚に教えてもらったのが高齢者雇用継続給付金です。
申請手続きは会社とハローワークの協力でスムーズに進み、毎月数万円を受け取れるようになりました。
そのおかげで、年金が本格的に支給されるまでの間、生活に余裕ができ、孫へのプレゼントや趣味の釣りにもお金を使えています。
『働いても収入が下がるだけ』と落ち込んでいた気持ちが前向きに変わりました。」
60代後半・女性(パート勤務/家計を支える主婦)
「夫が定年を迎えた後も働き続けることになり、私もパートを始めました。
夫の給料が減っても、この給付金のおかげで家計のバランスが保てています。
生活費や住宅ローンの残り、さらには自分の医療費にも余裕を持って備えることができるようになり、心強さを感じています。
最初は『申請が面倒そう』と敬遠していたのですが、一度手続きの流れを覚えてしまえば、それほど負担ではありませんでした。
むしろ『知らなかったら損をしていた』と実感しています。」
65歳直前・男性(転職後の再就職組)
「60歳で一度退職し、別の会社に再就職しました。
その際に給付金が受け取れるかどうか心配でしたが、条件を満たしていたため申請が可能でした。
前職のときより収入は減りましたが、給付金をプラスして考えると、以前とそれほど変わらない生活水準を維持できています。
また、再就職した会社は体力的に無理のない勤務体系だったので、健康面でも安心でした。
『再就職しても給付金があるなら大丈夫』という気持ちがあったからこそ、新しい挑戦ができたと思います。」
60代・女性(扶養や家族への影響を実感)
「私の場合、夫が給付金を受け取れることになり、世帯収入が予想以上に安定しました。
そのため、私自身がフルタイムで働く必要がなくなり、週3日の短時間勤務に切り替えることができました。
家族の時間も増え、両親の介護や孫の世話にも余裕を持って対応できています。
給付金は本人だけでなく、家族全体の生活を大きく変える力があるのだと実感しました。」
制度廃止を意識している人の声(60代前半・男性)
「最近『この制度が廃止される』というニュースを耳にして、とても不安になりました。
正直、今の生活は給付金があるから成り立っている部分が大きいです。
もしなくなったら、働き続けても家計はかなり厳しくなるでしょう。
制度があるうちにしっかり利用して、同時に年金や貯蓄を増やす計画を立てておくことが大切だと痛感しました。」
企業側の立場での声(人事担当者)
「社員が給付金を受け取れること自体は良い制度だと思います。
ただし、給与設計が難しくなるのも事実です。
例えば『給付金を受けたいから給与を調整してほしい』と依頼されると、人事制度全体のバランスに影響が出てしまいます。
それでも、従業員の生活を守るために制度の理解を深め、できる限り協力するようにしています。
結果的に従業員の働く意欲が維持できるので、企業にとってもプラスになると感じています。」
専門家のコメント(社会保険労務士)
「多くの方が誤解しているのは『給付金と年金の関係』です。
給付金自体は年金に直接影響しませんが、収入が増えることで在職老齢年金が減額されるケースがあります。
この部分を正しく理解していないと『なぜ年金が減ったのか』というトラブルにつながります。
相談に来られる方には、必ず『給付金・給与・年金の三つのバランス』を確認するようアドバイスしています。
正しく知識を持てば、給付金は老後の安心を支える強力な制度になるでしょう。」
Q&A集:高齢者雇用継続給付金に関するよくある疑問を徹底解説
Q1. 高齢者雇用継続給付金と年金は同時に受け取れますか?
A. 基本的には同時に受け取ることが可能です。
ただし注意すべき点は「在職老齢年金制度」です。
これは、年金を受け取りながら働いて一定以上の給与を得ると、年金が減額される仕組みのことです。
たとえば、60歳以降に月収と年金を合わせて47万円を超えると、厚生年金がカットされるケースがあります。
つまり「給付金そのものが年金を減らす」のではなく、「働いて得る収入全体が多いと年金が調整される」わけです。
この点を誤解してしまう方が多いため、必ず自分の収入状況を確認し、年金事務所でシミュレーションを行うことをおすすめします。
Q2. 60歳以降に転職した場合も給付金を受けられますか?
A. 条件を満たせば可能です。
再就職先で雇用保険に加入し、給与が60歳到達時の75%未満に下がっていれば対象となります。
ただし、転職先がパートや短時間勤務で雇用保険に加入できない働き方だった場合は対象外です。
また、前職と比べて大幅に給与が下がった場合は受給額が増えることもありますが、基準を超えて高い給与を得てしまうと給付金は出ません。
再就職を考えている方は、ハローワークで「給付金を受けられる働き方かどうか」を事前に確認してから行動すると安心です。
Q3. 受給するための具体的な手続きは難しいですか?
A. 初めての方には少し複雑に感じるかもしれませんが、流れを理解すれば決して難しくありません。
大まかな流れは以下の通りです。
勤務先から「賃金証明書」などの必要書類を発行してもらう
本人確認書類や給与明細を用意する
ハローワークに提出し、申請する
以後は2か月ごとに更新手続きを行う
会社の人事部やハローワークの職員がサポートしてくれるので、一人で悩む必要はありません。
「申請が面倒だからやめてしまう」のは非常にもったいないので、最初だけ少し頑張って手続きを覚えましょう。
Q4. 支給額はどのくらいもらえるのですか?
A. 支給額は人によって異なります。
計算方法は「60歳時点の賃金」と「現在の賃金」の差によって決まるため、給与が大きく下がった人ほど多く受け取れる仕組みです。
例えば、60歳のとき月収30万円だった人が再雇用で月収20万円になった場合、差額の一部を国が補填してくれます。
目安としては数万円程度が多く、月3〜5万円程度の支給を受けるケースがよく見られます。
ただし「上限額・下限額」があるため、必ず自分のケースをハローワークで確認する必要があります。
Q5. 支給はいつまで続くのですか?
A. 原則として60歳から65歳までの5年間が支給期間です。
ただし「65歳を過ぎた場合」は支給対象外となります。
そのため、あくまでも「年金本格支給までの繋ぎ」として利用する制度だと理解しておくとよいでしょう。
また、制度改正により今後は支給対象や期間が短縮される可能性もあるため、常に最新の情報をチェックしておくことが大切です。
Q6. 制度が廃止されると聞いたのですが、本当ですか?
A. はい、制度は段階的に廃止される方向で進んでいます。
背景には「高齢者の就業機会が広がっていること」や「年金制度との二重支援を見直すべき」という議論があります。
ただし、すぐに一斉廃止されるわけではなく、経過措置が設けられています。
現在すでに給付を受けている人は当面継続されるケースが多いため、対象となる方は早めに手続きを済ませることをおすすめします。
Q7. 配偶者や家族への影響はありますか?
A. はい、間接的な影響があります。
例えば、夫が給付金を受け取ることで世帯収入が安定すれば、妻の就労スタイルを調整できたり、子ども世代への仕送り負担を減らせたりします。
一方で、配偶者が扶養に入っている場合、給付金や給与の増減によって扶養から外れる可能性があるため注意が必要です。
つまり、この制度は「本人だけの問題」ではなく「家族全体の生活設計」に影響を与える制度だと言えるでしょう。
Q8. 在職老齢年金のカットを避ける方法はありますか?
A. 完全に避けることは難しいですが、働き方を工夫することで調整は可能です。
例えば、収入が多すぎて年金がカットされる場合は、勤務日数を減らしたり、パート勤務に切り替えたりする方法があります。
また、副業や在宅ワークを選んで「給与収入ではなく事業所得」として得るなど、収入の形態を工夫する人もいます。
ただし、税金や社会保険への影響もあるため、必ず専門家に相談しながら調整するのが安心です。
Q9. この制度を知らずに受け取っていなかったらどうなりますか?
A. 申請しなければ給付は受けられません。
制度は「自動的に支給されるもの」ではなく、必ず申請が必要です。
知らずに過ごしてしまうと、本来もらえるはずだった数十万円〜数百万円を逃すことになりかねません。
特に地方では「制度の存在を知らないまま定年を迎える」人も少なくありません。
情報を早めに入手し、該当する場合は必ず申請しましょう。
Q10. 会社が非協力的だった場合はどうすればいいですか?
A. 給付金の申請には会社の協力が必要ですが、万一非協力的な場合は直接ハローワークに相談してください。
ハローワークは制度の窓口ですので、会社にどう説明すべきかも含めてアドバイスをしてくれます。
また、社会保険労務士や労働組合に相談する方法もあります。
「制度を知らない」「書類作成を面倒がる」など会社の理解不足が原因の場合もあるため、外部の専門家を巻き込むのも有効です。
【まとめ】
高齢者雇用継続給付金を正しく理解し、老後の安心へつなげるために
高齢者雇用継続給付金は、定年を迎えて給与が下がった高齢者にとって、大きな経済的支えとなる制度です。
「給与が減っても働き続けたい」「年金が本格的に支給されるまで生活を安定させたい」という人にとって、この制度はまさに「架け橋」となります。
しかし、その仕組みは単純ではなく、メリットとデメリットが表裏一体で存在します。
年金との関係、在職老齢年金制度による調整、申請の複雑さ、そして今後の制度廃止の見通しなど、知っておかないと損をするポイントが多いのです。
特に重要なのは、次の点です。
- 対象期間は原則60歳から65歳までの5年間 に限定される
- 給与が60歳時点の75%未満に下がった場合に支給 される
- 年金と同時に受給可能だが、在職老齢年金の調整に注意 が必要
- 申請手続きは会社とハローワークを通じて行い、2か月ごとに更新 が必要
- 制度は将来的に縮小・廃止が見込まれており、利用できる間に活用するのが得策
これらを正しく理解していないと、「思ったより年金が少なかった」「申請を忘れて給付が止まった」などのトラブルに直面することになります。
一方で、この給付金を上手に活用すれば、ライフプラン設計の選択肢が広がります。
生活費や医療費の補填はもちろん、趣味や旅行、学び直し、副業や新しい働き方への挑戦など、人生の後半をより豊かにする資金源となるのです。
また、家族全体にとっても大きな意味を持ちます。
夫婦の生活設計を支え、子ども世代の経済的負担を軽減し、安心して「自分らしい老後」を描けるようになります。
制度は残念ながら永遠ではなく、2025年以降は縮小・廃止に向けて進んでいくとされています。
そのため、「制度が使えるうちに申請しておく」ことが今後の生活を安定させる鍵となります。
同時に、給付金に頼るだけでなく、年金・給与・貯蓄を総合的に組み合わせてライフプランを構築する姿勢も大切です。
最後に、この制度を最大限に活用するためのポイントを整理します。
- まずは自分が対象になるかを確認する(給与・雇用保険加入・年齢条件)
- 申請の流れと必要書類を把握する(会社とハローワークの連携が不可欠)
- 年金や扶養、家族への影響を考慮する
- 在職老齢年金とのバランスを必ずチェックする
- 制度廃止に備えて、早めに行動しライフプランを調整する
高齢者雇用継続給付金は、ただのお金の支援制度ではなく「人生の後半をどう生きるか」を考えるきっかけを与えてくれる仕組みです。
制度を知っているかどうかで、老後の安心度は大きく変わります。
情報を正しく理解し、計画的に活用すれば、定年後も安心して働き続けられ、心豊かなセカンドライフを実現することができるでしょう。
最後までお読みいただきまして
ありがとうございました。