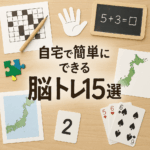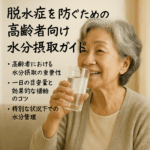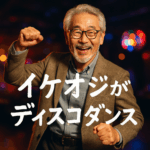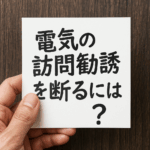75歳以上の医療費が2倍に?最新制度改正と負担軽減の全ポイント解説

医療費負担増加に直面している75歳以上の方・家族必見!改正内容や手続き方法、負担を抑えるコツを詳しくご案内。医療費負担増に備える!75歳以上の家計防衛術と公的支援の活用法。

高齢者と医療費の新しい課題

Contents
- 1 後期高齢者医療制度とは?
- 2 医療費の自己負担が2倍に?
- 3 75歳以上が直面する医療費の引き上げ
- 4 自己負担額の具体的な推移
- 5 「3割負担」の影響とは?
- 6 限度額と高額療養費の仕組み
- 7 保険料の上昇と所得の関係
- 8 生活に与える影響を考える
- 9 入院費と食費の合算
- 10 その他の負担、生活費はどうなる?
- 11 非課税世帯の特例について
- 12 助成制度の活用方法
- 13 健康保険を利用した負担軽減
- 14 申請手続きの流れと注意点
- 15 必要書類と手続きの流れ
- 16 いつ申請すればいいのか?
- 17 受給者の体験談
- 18 今後の制度改正の可能性
- 19 高齢者のための医療政策の方向性
- 20 社会保障の観点からの考察
- 21 医療費の自己負担は具体的にいくら?
- 22 75歳以上の支援制度はどうなっているか?
- 23 医療費の返ってくるケースとは?
- 24 重要なポイントの整理
- 25 患者に求められる対応策
- 26 あらためて知るべきこと
後期高齢者医療制度とは?
日本の高齢者医療制度の中でも、特に75歳以上の方を対象とする「後期高齢者医療制度」は、多くのシニア世代が加入している公的保険制度です。これは、2008年に創設された制度で、それまでの老人保健制度から移行したもの。医療サービスをより安定的かつ公平に受けられるように設計されています。加入者は原則として75歳以上(または一定の障がい認定を受けた65歳以上)となっており、市区町村ごとに設置される「後期高齢者医療広域連合」が保険運営を担当します。制度の特徴は、基本的に現役世代と比べて医療費自己負担割合が抑えられている点にあり、これまで多くの高齢者が安心して医療を受けられる仕組みとなってきました。
医療費の自己負担が2倍に?
近年、この後期高齢者医療制度を巡り、「医療費の自己負担が2倍になる」といったニュースや話題が急増しています。特に2022年(令和4年)10月から導入された制度改正では、一定所得以上の75歳以上の方について、これまで1割だった医療費自己負担が2割へと引き上げられました。これによって、従来よりも診察・検査・治療などの受診時に支払う金額が増えるケースが出てきています。「年金暮らしの中で家計への影響が心配」「今後さらに負担が増えるのでは」といった不安の声も多く、高齢者世帯やその家族から大きな関心が寄せられています。
75歳以上が直面する医療費の引き上げ
特に注意したいのは、今回の改正によってすべての高齢者の負担が一律に増えたわけではないという点です。医療費自己負担の割合アップは、単身で年収200万円以上、夫婦世帯で合計年収320万円以上といった「一定以上の所得がある人」が対象となっています。一方で、それ未満の世帯はこれまで通り1割負担のままです。しかし、全体としては「将来的に医療費負担の増加傾向が続くのでは?」という不安や、社会全体の高齢化に伴う財政圧迫への警戒感も広がっています。
新制度の細かな条件や、個人ごとの負担割合の違いについては市区町村や医療広域連合の案内、もしくはかかりつけ医や地域包括支援センターで確認できます。「うちの場合はどうなるの?」と疑問や不安がある場合は、必ず最新の情報を直接問い合わせるのがおすすめです。
医療費の負担構造の現状

自己負担額の具体的な推移
75歳以上の高齢者にとって、医療費の自己負担額は家計を左右する大きなポイントです。従来、後期高齢者医療制度では多くの方が「1割負担」で医療を受けてきましたが、令和4年10月からは所得によっては2割負担、さらに現役並み所得者は3割負担というように複数の区分が生まれています。
たとえば、今まで1,000円の医療費を支払っていた人が2割負担になると2,000円となり、通院頻度や治療内容によっては年間で数万円の増額になることも。診察だけでなく薬局での薬代やリハビリなど、医療にかかわる全ての支払いが対象です。毎月一定額までの自己負担で済む「高額療養費制度」もありますが、利用には条件や申請手続きが必要です。実際の自己負担額は、所得区分や医療機関の利用頻度によって異なりますので、事前にシミュレーションしておくと安心です。
「3割負担」の影響とは?
高齢者でも「現役並み所得者」と判定される場合は、医療費の自己負担が3割となります。現役世代と同様の負担率ですが、高齢者の場合は年金収入や資産状況を考えると生活への影響がより大きくなりがちです。医療費が高額になった場合、支出が生活費全体に占める割合も増えやすく、他の支出(食費・光熱費・趣味など)を削らざるを得ないケースも見られます。特に慢性疾患や長期療養が必要な方にとっては、医療費負担が生活設計や老後資金に直結する重要なテーマです。
限度額と高額療養費の仕組み
医療費が高額になった場合、「高額療養費制度」により、自己負担額には月ごとの上限(限度額)が設けられています。例えば、一般的な所得区分であれば、1カ月あたりの自己負担額が18,000円程度を超えた分はあとから払い戻される仕組みです。ただし、所得区分や医療機関ごとに計算が異なるため、自分の条件に合った限度額を確認しておくことが大切です。限度額認定証の申請をしておくことで、医療機関での支払いを最初から上限内に抑えることもできます。分かりにくい場合は、地域の窓口や社会保険労務士に相談するのもおすすめです。
改正によって何が変わったのか
令和4年(2022年)10月の制度改正により、75歳以上の後期高齢者医療制度加入者のうち、一定以上の所得がある人については医療費の自己負担割合が1割から2割へ引き上げられました。これは「社会全体の医療費増加に伴い、現役世代の負担軽減と高齢者間の公平な負担」を目的とした措置です。対象となるのは、単身世帯で年収200万円以上、夫婦世帯で合計年収320万円以上の方です(この判定は所得金額ベースで行われます)。
今回の改正で「2割負担」になる高齢者は全体の約20%程度とされていますが、今まで通り1割負担の方も依然として多数います。つまり、「一定以上の所得がある方」だけが対象となることがポイントです。加えて、急激な負担増とならないように“経過措置”が設けられており、初年度(2022年度)は外来医療費について1か月の負担増加が最大3,000円までに抑えられる仕組みになっています。

保険料の上昇と所得の関係
同じく、保険料も年々上昇傾向にあります。高齢化社会の進行と医療費全体の増大が背景にあり、保険料の設定や見直しは各自治体ごとに行われています。一般的には、所得の高い方ほど保険料も高くなる“応能負担”の原則が適用されており、年金やその他の収入が多い方は毎月の保険料負担が重くなりがちです。逆に、低所得世帯には減免措置や軽減策が用意されているので、自治体の案内を必ずチェックしましょう。
生活に与える影響を考える
この改正により「月々の医療費・保険料負担が家計に直結するようになった」と感じる高齢者世帯も少なくありません。特に、持病で通院頻度が高い方や、複数の医療機関を受診する方は、これまでより自己負担額が明確に増えるため、生活設計の見直しや家計管理が必要になります。一方で、制度としては高額療養費制度や各種減免措置も用意されているため、「知らずに損をする」ことがないよう情報収集が重要です。気になる点や不安があれば、市区町村や地域包括支援センター、かかりつけ医などへ早めに相談しましょう。
高齢者世帯の負担の実態

入院費と食費の合算
高齢者になると医療機関への受診や入院の頻度が増えやすく、入院時の自己負担は「医療費」と「食事療養費(食費)」に分かれます。医療費はこれまで説明した1割・2割・3割負担となり、食費は別途定額での自己負担となります。例えば、1食あたり460円(2024年現在・一般的なケース)の負担額がかかり、1か月入院すれば食費だけで2万円近くかかることも。これに加えて入院中の部屋代(差額ベッド代)や日用品代も自己負担となります。高額療養費制度を利用すれば医療費部分の上限はありますが、食費や差額ベッド代などは制度の対象外です。
その他の負担、生活費はどうなる?
入院や外来の医療費のほかにも、介護サービス利用料や福祉用具のレンタル代、公共料金、家賃、食費、日用品など生活費全体への影響が大きくなります。特に年金収入のみで暮らしている世帯では、医療費・保険料・介護費用の増加がそのまま生活費圧迫につながるため、家計管理の見直しが欠かせません。医療・介護の出費が増えたことで、日常の食事や趣味、交際費などに制限がかかるケースも多く、「医療費が増えた分、生活の質を落とさざるを得なかった」という実例も少なくありません。
非課税世帯の特例について
生活保護や住民税非課税世帯の場合、医療費・入院時の食費・介護費用などに各種軽減措置や減額特例があります。たとえば、入院時の食費負担が1食100円台まで軽減される場合もあり、高額療養費制度の自己負担限度額も低く設定されています。介護サービスや医療費の助成も充実しているため、該当する方は必ず市区町村や社会福祉協議会に申請・相談することが大切です。「知らなかったから使えなかった」とならないよう、最新の福祉情報や制度を常にチェックしましょう。
医療費負担の軽減策

助成制度の活用方法
高齢者世帯の医療費負担を減らすためには、さまざまな助成制度や公的支援を活用することが重要です。たとえば、高額療養費制度は、医療費が一定額を超えた際に超過分が払い戻される仕組みです。他にも、自治体独自の医療費助成(例えば「高齢者医療費助成制度」や「難病医療費助成」など)や、生活保護・障害者手帳など各種福祉制度を組み合わせることで、実質的な負担を大きく軽減できます。各市区町村の窓口や福祉相談員に相談すれば、個人の状況に合った制度を教えてもらえるので、困ったときはまず相談が基本です。
健康保険を利用した負担軽減
後期高齢者医療制度自体も公的健康保険の一種で、原則1割または2割(現役並み所得者は3割)の自己負担で済みます。加えて、複数の医療機関を利用した場合でも合算して高額療養費制度の適用を受けられるケースもあります。薬局での薬代やリハビリ、在宅医療、訪問診療なども健康保険が適用されるため、民間医療保険との併用や見直しもおすすめです。もし手続きや対象範囲がわかりにくい場合は、保険証や医療機関の窓口で相談してみましょう。
申請手続きの流れと注意点
高額療養費や各種助成制度の利用には「申請」が必要です。一般的には、医療機関の領収書や明細書、保険証、印鑑など必要書類を揃えて市区町村窓口や医療広域連合へ申請します。申請書類に不備があると審査が遅れるので、記載漏れ・押印・添付資料など細かい点まで確認を。すでに医療費を支払った後でも、一定期間内であれば「還付請求」が可能な場合も多いので、あきらめずに相談しましょう。わからない点や迷った時は、地域包括支援センターや社会福祉協議会、医療機関の相談員に尋ねると安心です。
高額療養費の申請方法

必要書類と手続きの流れ
高額療養費制度を利用するには、まず医療費の支払いが一定額(自己負担限度額)を超えた月ごとに申請を行います。必要な書類は、医療機関からもらう領収書・診療明細書、健康保険証、印鑑、本人確認書類(運転免許証など)、場合によっては口座情報や限度額適用認定証なども求められます。市区町村の担当窓口や医療広域連合へ持参・郵送で申請できます。申請後、内容に問題がなければ数週間から2カ月程度で払い戻しが振込まれます。
いつ申請すればいいのか?
原則として、自己負担限度額を超えた月の翌月以降に申請が可能です。申請には期限(多くは診療月の翌月から2年以内)があるため、早めに手続きするのがおすすめです。なお、「限度額適用認定証」を事前に取得して医療機関に提示しておけば、窓口支払い時から上限額で済むので、急な入院や高額医療が予想される場合は事前準備も大切です。
受給者の体験談
「突然の入院で不安だったが、病院の相談員に教えてもらい高額療養費制度を利用。申請書類をそろえて提出したら、約1カ月後に払い戻しがあり経済的に助かった」「複数の病院にかかっていたので合算できることを知らなかったが、窓口で教えてもらえて大きな節約になった」「最初は書類が面倒に感じたが、担当者が親切にサポートしてくれて安心して申請できた」など、多くの方が実際に利用し、家計負担軽減に役立てています。わからないことがあれば、遠慮せずに病院の相談員や市区町村窓口に相談しましょう。
医療費負担の将来展望

今後の制度改正の可能性
今後も日本の高齢化が進む中で、医療費負担のあり方や制度そのものの見直しは避けられないテーマとなっています。近年の改正の流れを見ると、「一定所得以上の高齢者の負担増」「所得に応じた負担割合の細分化」などが今後も進む可能性が高いです。また、医療財政の持続性を保つために、今後さらに自己負担割合や保険料の見直し、新たな助成制度の導入などが議論されるでしょう。医療サービスの質と公平性をどう確保するかが、今後の大きな課題です。
高齢者のための医療政策の方向性
医療費負担増加の中でも、高齢者が安心して医療を受けられる社会を実現することが重要です。今後は「予防医療や健康づくりの推進」「在宅医療や地域包括ケアの充実」など、自立支援や生活の質(QOL)向上を重視した政策が拡大していく見込みです。特に認知症対策や介護との連携、慢性疾患の予防・管理など、多職種が協働する仕組みづくりが求められています。
社会保障の観点からの考察
高齢化社会を支える社会保障制度は、年金・医療・介護の連携と財源確保がカギです。医療費の伸びを抑えつつ公平な負担を実現するため、保険料・税負担・給付水準のバランス調整や、現役世代・高齢者世代双方が納得できる制度運営が不可欠です。今後はデジタル化・ICT活用による効率化や、地域住民の参加による“支え合い”の社会基盤づくりも課題となるでしょう。持続可能で信頼できる医療・社会保障を目指し、国民一人ひとりが関心を持って考えることが大切です。
75歳以上の医療費に関するよくある疑問

医療費の自己負担は具体的にいくら?
75歳以上の自己負担割合は「1割」が基本ですが、一定所得以上なら2割、現役並み所得者は3割です。例えば、1回の診察費が1,000円なら、1割負担の人は100円、2割負担の人は200円、3割負担の人は300円となります。毎月・毎回の支払いなので、通院や治療が多い場合は年額で数万円単位の負担差が出ることも。さらに高額療養費制度で上限設定もあるため、実際の支払いには個人差があります。
75歳以上の支援制度はどうなっているか?
高額療養費制度、医療費助成、介護サービス助成、住民税非課税世帯向けの軽減策など複数の支援制度があります。たとえば、高額療養費制度は月ごとの医療費自己負担に上限を設け、超過分は払い戻しされます。生活保護や住民税非課税世帯なら医療費や入院時の食費・介護費用も軽減措置あり。自治体によっては独自の高齢者医療助成もあるので、窓口で相談・申請が大切です。
医療費の返ってくるケースとは?
高額療養費制度を利用した場合や、後から申請して払い戻しが認められる場合(還付申請)が該当します。自己負担限度額を超えて支払った医療費分は後日払い戻し。複数の医療機関や薬局での支払いも合算できる場合があるので、領収書は必ず保存を。条件や手続きは自治体や保険者によって異なるため、疑問は早めに窓口や相談員に確認しましょう。
高齢者医療費の今後
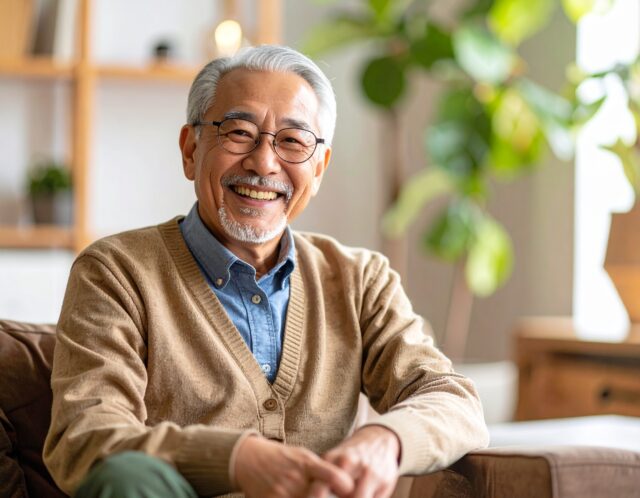
重要なポイントの整理
高齢者の医療費負担は、今後も高齢化社会の進行とともに見直しや改正が続く見込みです。「所得区分による自己負担の変化」「高額療養費制度などの各種支援策の活用」「市区町村や医療機関の相談窓口の利用」が今後ますます重要になります。最新の制度情報を定期的に確認し、家計や生活設計にしっかり活かすことがポイントです。
患者に求められる対応策
自己負担が増える状況下では、無理なく医療を利用するための計画性が大切です。高額療養費制度や医療費助成、介護保険などを最大限に活用し、領収書や医療費控除に必要な書類は必ず保管しましょう。また、急な医療費負担にも備えて、日ごろから健康管理・予防医療にも積極的に取り組むことが今後ますます求められます。家族と情報共有し、不安があれば早めに相談や申請を心がけましょう。
あらためて知るべきこと
高齢者医療費制度は複雑で個別性も高いため、「知らなかった」「手続きを忘れて損をした」とならないよう、気になることがあれば早めに専門窓口や病院の相談員に相談しましょう。支援策や最新情報を上手に活用して、少しでも安心して医療を受けられるよう備えることが、これからの高齢者医療費対策の鍵です。
高齢者医療費の今後に関するQ&A

Q1:今後も医療費の自己負担割合は増えるのでしょうか?
A1:日本の高齢化が進み、医療費全体が増加している現状では、今後も「所得に応じた自己負担割合の見直し」や「新たな負担区分の追加」など、自己負担割合が増える可能性は否定できません。ただし、急激な変更の際は経過措置や上限設定などの緩和策がとられることが多いです。政府や厚生労働省から発表される最新情報を定期的に確認しましょう。
Q2:自己負担が増えた場合、どんな支援策がありますか?
A2:自己負担割合が増えても、高額療養費制度や各種助成制度、介護保険や生活保護、住民税非課税世帯向けの軽減策など、多様な支援策が活用できます。領収書や明細は必ず保管し、申請に必要な書類や手続き方法を早めに自治体窓口で相談してください。また、自治体ごとに独自の助成や福祉サービスがある場合もあるので、地域の広報やホームページも定期的にチェックしましょう。
Q3:家計の負担が増えたときの生活設計のポイントは?
A3:医療費や保険料の増加が家計を圧迫する場合は、まず家族や専門家と相談し、生活設計の見直しを検討しましょう。高額療養費制度や介護保険、各種助成制度の利用を徹底し、節約できる支出(光熱費や交際費など)を見直すことも大切です。健康管理や予防医療に努めることで、将来的な医療費増加のリスクも減らせます。自治体の生活相談や社会福祉協議会も積極的に活用しましょう。
Q4:申請や手続きが面倒で分かりにくい場合は?
A4:医療費や福祉制度の申請・手続きは複雑に感じがちですが、市区町村の相談窓口や地域包括支援センター、病院の相談員などが無料でサポートしてくれます。書類の書き方や必要書類の確認、申請書の提出なども一緒に進めてもらえる場合が多いので、不安なときは一人で抱え込まず、積極的に相談してみてください。
Q5:今後のために家族で話し合っておくべきことは?
A5:急な入院や介護、医療費の増加などに備えて、家族であらかじめ生活設計や今後の方針、希望する治療や生活の質について話し合っておくことがとても大切です。資金計画や使える制度、万が一の際の手続きなどを共有し、「知らなかった」「相談しておけばよかった」と後悔しないための準備をしておきましょう。
【まとめ】

75歳以上の医療費負担とこれからの対策
本記事では、75歳以上の高齢者を取り巻く医療費負担の現状と、令和4年の制度改正による変化、さらに今後の見通しや対策までを詳しく解説しました。
近年は、一定以上の所得がある方を中心に医療費の自己負担割合が1割から2割、場合によっては3割にまで引き上げられるなど、負担増加の傾向が続いています。加えて、入院時の食費や部屋代、介護・福祉費用なども家計に大きく影響し、生活設計や老後資金の見直しがますます重要になっています。
ただし、高額療養費制度や各種助成、住民税非課税世帯向けの軽減策など、公的な支援制度も充実しているため、積極的に情報収集と制度活用を行うことで、実質的な負担を抑えることが可能です。申請や手続きに迷ったときは、市区町村や病院・地域包括支援センターに早めに相談しましょう。
今後も制度改正や社会環境の変化が見込まれるなか、日ごろから健康管理に努め、家族や専門家と連携して生活設計を柔軟に見直すことが大切です。「知らなかった」「もったいない」で損をしないよう、常に最新情報をチェックし、備えを万全にしておきましょう。
最後までお読みいただきまして
ありがとうございました。