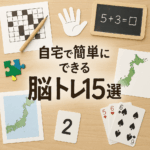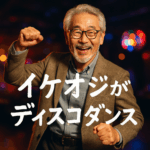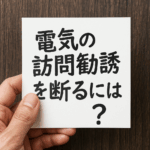高齢者の脱水症対策と毎日の水分補給のコツ|家族で学ぶ高齢者の水分管理と最新ポイント
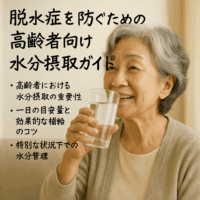
高齢者が脱水症を防ぐために欠かせない水分摂取量や効果的な補給方法を徹底解説。健康長寿を叶えるための実践ポイントも紹介します。高齢者が健康長寿を叶えるための水分摂取量の目安と失敗しない実践法。
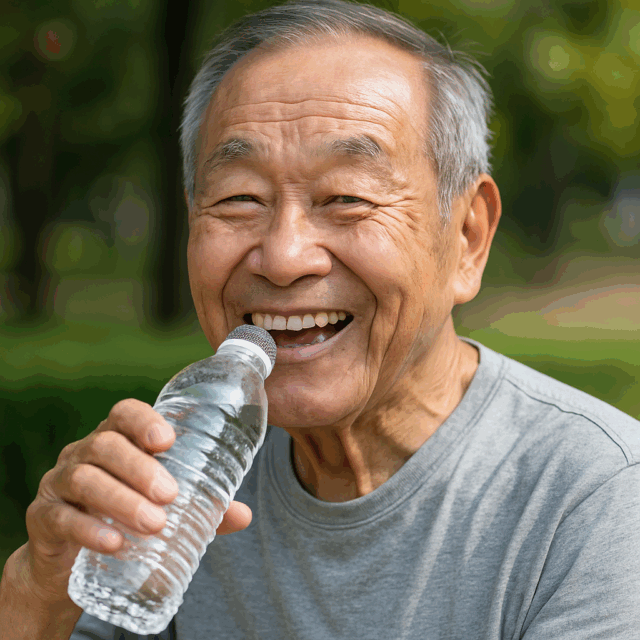
高齢者における水分摂取の重要性

Contents
- 1 水分摂取量が足りないとどうなるか
- 2 脱水症のリスクと高齢者の健康
- 3 厚生労働省が定める水分摂取ガイドライン
- 4 年齢や体重に基づく計算方法
- 5 高齢者に必要な水分摂取量の具体例
- 6 1日あたりの飲み物と食事からの水分摂取
- 7 日常生活での水分補給習慣
- 8 高齢者におすすめの飲み物と食べ物
- 9 無理なく水分を摂取するための方法
- 10 介護者ができる声かけとサポート
- 11 本人が意識するためのポイント
- 12 家族で取り組みたい水分管理
- 13 熱中症や脱水状態を予防するための対策
- 14 旅行や外出時の水分摂取の注意点
- 15 体調による水分摂取量の調整
- 16 果物やゼリーは水分補給に適しているか?
- 17 飲み物の取りすぎのリスクについて
- 18 尿の色から分かる水分不足のサイン
水分摂取量が足りないとどうなるか
高齢者にとって水分補給は、健康を保つうえで非常に重要なポイントです。
年齢を重ねると体内の水分量自体が若い頃より減少し、さらに「のどの渇き」を感じる感覚も鈍くなっていきます。
そのため、「まだ大丈夫」と思っていても、実際は体が水分不足に陥っていることが珍しくありません。
水分が足りない状態が続くと、まず現れやすいのが便秘や食欲不振、頭痛、ふらつきといった日常の不調です。
また、体温調節もうまくいかなくなり、ちょっとした暑さや寒さにも弱くなります。
さらに進行すると、脱水症や熱中症、ひどい場合は意識障害や急激な体調悪化を引き起こすこともあるため注意が必要です。
高齢者の場合、もともと筋肉量が減り体に蓄えられる水分が少なくなっているため、若い世代以上に水分補給をこまめに行う必要があります。
特に暑い夏や運動をしたとき、風邪や下痢で体調を崩しているときなどは、意識して多めに水分を摂ることが大切です。
家族や周囲の方が「今日は水分足りてる?」と声掛けをするだけでも、日々の体調維持につながります。
脱水症のリスクと高齢者の健康
脱水症とは、体の中の水分と電解質(塩分やミネラル)が不足している状態を指します。
高齢者は、加齢に伴う体内水分量の減少に加え、腎機能や内臓機能の低下、降圧剤や利尿剤など薬の副作用、また持病や慢性的な病気の影響などで脱水症に陥りやすい特徴があります。
脱水症が進行すると、めまいや立ちくらみ、食欲低下、皮膚の乾燥、頻尿や排尿回数の減少といった症状が現れやすくなります。
重度の場合は、意識障害やけいれん、心筋梗塞・脳梗塞など命に関わる重大な健康被害に直結することも。
また、脱水によるふらつきや筋力低下が原因で転倒・骨折のリスクが上がり、寝たきりや介護状態へ進行する例も少なくありません。
高齢者は、暑さや発熱、下痢・嘔吐などで急激に体から水分を失いやすいため、特に気温が高い時期や体調不良時は「脱水症対策」を意識した生活が不可欠です。
厚生労働省が定める水分摂取ガイドライン
日本の厚生労働省は、健康な成人(高齢者を含む)に対し「1日1.2リットル以上の水分を飲み物から摂取する」ことを推奨しています。
これは食事に含まれる水分も合わせれば、1日トータルで約2リットル前後の水分摂取が理想的とされています。
高齢者は特に、暑い季節や発熱・下痢など体から水分が失われやすい場面では、普段より意識的に多めの水分摂取を心がけましょう。
水分は「のどが渇いた」と感じる前から、1日を通して少量ずつこまめに取ることが大切です。
朝起きたとき・食事の前後・入浴の前後・就寝前など、生活のさまざまなタイミングで意識的に水分を摂る習慣をつけると、脱水症の予防につながります。
飲み物は、水や麦茶、ノンカフェインのお茶、スポーツドリンク、経口補水液などが理想的。
カフェインやアルコールには利尿作用があるため、これらばかりに頼るのは避けましょう。
家族や介護者が「水分チェックシート」などで記録するのもおすすめです。
高齢者の一日の水分摂取量の目安

年齢や体重に基づく計算方法
1日に必要な水分摂取量は、年齢や体重、活動量によって異なります。
健康な高齢者の場合、一般的な目安は「体重1kgあたり約30ml」です。
たとえば、体重50kgの方なら「50kg×30ml=1,500ml」、60kgの方なら「60kg×30ml=1,800ml」が1日の目安となります。
これに加えて、発汗量の多い夏場や運動をした日はさらに200~400ml程度をプラスするのが理想です。
なお、腎臓や心臓の病気がある方、利尿剤などの薬を服用している方は、必ず主治医の指示を仰ぎましょう。
高齢者に必要な水分摂取量の具体例
高齢者は、若い頃よりも食事量が減る傾向があるため、飲み物からの水分摂取を積極的に心がける必要があります。
体重別で見ると、
・体重40kg→約1,200ml
・体重50kg→約1,500ml
・体重60kg→約1,800ml
が一つの目安です。
この中には食事中の水分(味噌汁、スープ、果物、ゼリー、ヨーグルトなど)も含まれます。
「食が細くなった」と感じている場合は、飲み物で水分をカバーする意識が大切です。
日中はもちろん、朝の寝起きや入浴後、散歩やリハビリ運動のあとなど、汗をかく場面や体が乾きやすいタイミングでの補給が重要です。
1日あたりの飲み物と食事からの水分摂取
食事から得られる水分は全体の約半分ほどと言われ、1日1.0リットル前後は飲み物で摂取する必要があります。
理想的なのは、コップ1杯(200ml)を「朝起きたとき」「食事のたび」「間食やおやつ時」「入浴の前後」「寝る前」など、1日5~8回に分けて飲む方法です。
水や麦茶、ノンカフェインのお茶、経口補水液をバランス良く取り入れましょう。
スポーツドリンクは熱中症予防や体調不良時には有効ですが、普段使いには糖分に注意しましょう。
利尿作用の強いカフェイン飲料やアルコール類は、逆に脱水を招く恐れがあるためほどほどに。
水分補給は「のどが渇く前」「体が欲している前」に行うのが最大のポイントです。
また、「自分は飲み物が苦手」という方は、ゼリーやプリン、果物など水分を多く含む食材を上手に利用しましょう。
家族や周囲の人も、「水分補給した?」と日々声かけをすることで、高齢者の脱水予防をサポートできます。
こまめな水分補給で、健康的で安心な毎日を過ごしましょう。
効果的な水分補給のコツ

日常生活での水分補給習慣
高齢者が健康を維持し、脱水症を防ぐためには、毎日の生活リズムの中に自然に「こまめな水分補給」を組み込むことがとても大切です。
朝起きてすぐ、食事の前後やおやつタイム、入浴や外出・散歩の前後、就寝前など、生活の中の“タイミング”を決めて意識的に水分を摂るようにすると、無理なく習慣化できます。
水やお茶などの飲み物を目につきやすい場所に常に置いておいたり、専用のコップや水筒を用意したりすることで、気がついた時にすぐ飲める環境を作ることがポイントです。
「のどが渇いた」と感じる前から定期的に少しずつ飲むようにし、朝・昼・夕・夜の一日4回以上、できれば5~8回程度に分けて摂取すると、脱水のリスクを大きく減らせます。
また、暑い時期や発汗が多い日、体調がすぐれないときには、通常よりも多めに水分を取ることを意識しましょう。
家族や介護者も、「今お茶にしませんか?」「水分タイムですよ」と自然に声かけをすることで、高齢者本人も意識が高まり、毎日の水分補給がより続きやすくなります。
高齢者におすすめの飲み物と食べ物
高齢者の水分補給には、体に負担が少なく毎日飲みやすいものを選ぶことが重要です。
基本は水や麦茶、ほうじ茶などノンカフェインで利尿作用が少ないものを中心に、暑い日はスポーツドリンクや経口補水液を上手に取り入れるのも良いでしょう。
カフェイン入りの緑茶やコーヒー、紅茶は飲みすぎると利尿作用で体内の水分が失われやすいため、バランスよく。
また、乳酸菌飲料やジュース、フルーツ味のゼリー飲料なども気分転換や食欲がない時に取り入れやすいですが、糖分の摂りすぎには注意が必要です。
食事面では、みそ汁やスープ、煮物といった汁物、みずみずしい果物(みかん・スイカ・梨・キウイなど)、ヨーグルトやプリン、ゼリーといった水分を多く含む食品を積極的に取り入れましょう。
特に食欲が落ちている場合や「水分を飲むのが苦手」という方は、こうした食品で水分摂取量を補う工夫も有効です。
無理なく水分を摂取するための方法
「一度にたくさん飲むのが苦手」「水分を飲むのが億劫」という高齢者も少なくありません。
そんな時は、一回の摂取量を小さなコップ1杯分(100~150ml程度)にして、回数を増やす方法がおすすめです。
飲むタイミングを決めたり、カラフルで気分の上がる専用コップやストロー、お気に入りのマグカップを使ったりして「飲みたくなる工夫」を加えるのも効果的です。
また、冷たい飲み物が苦手なら常温や温かい飲み物、風味付けにレモンや梅干し、シソなどを加えることで飲みやすさもアップします。
ゼリーやフルーツなどを食事やおやつ代わりに摂取すれば、楽しみながら自然と水分補給ができます。
「水分摂取=義務」ではなく、「美味しい・楽しい・気分転換になる」というポジティブな気持ちで日々取り組むことが長続きのコツです。
水分摂取量を管理するための声かけ

介護者ができる声かけとサポート
介護者やご家族は、高齢者が無理なく水分補給できるようにサポートする役割を担います。
「そろそろ水分タイムにしませんか?」「おやつと一緒にお茶もどうですか?」といった優しい声かけを、日常の中で自然に行いましょう。
一緒にお茶を飲む時間を設けたり、みんなで水分補給をするルーティンを作ることで、楽しく習慣化できます。
また、飲み物を見やすい場所に置く、好きなデザインのコップを使うなど、「自分から飲みたくなる環境づくり」も大切です。
日々の水分摂取量を「水分チェック表」やカレンダーに記録することで、本人も進捗がわかりやすくなり、達成感や意識づけにつながります。
調子が悪い日や特に暑い日、運動をした日などは、積極的に「あともう1杯どうですか?」と声かけを強化しましょう。
本人が意識するためのポイント
高齢者本人も、「のどが渇く前に飲む」「1日何回飲んだかメモする」など簡単な目標や記録をつけることで、日々の水分補給を自然と意識できるようになります。
飲み物の種類やコップの形、色、温度を変えたり、気分や体調に合わせて工夫することで、楽しみながら続けやすくなります。
好きなフルーツやゼリーを取り入れる、友人や家族と一緒に「水分タイム」を設けるなど、コミュニケーションのきっかけとしても活用できます。
「今日はたくさん飲めた」「昨日より1杯多く飲めた」など、ちょっとした達成感や前向きな気持ちが続ける秘訣です。
家族で取り組みたい水分管理
水分摂取は高齢者本人だけでなく、家族みんなで声をかけ合い、習慣化することがとても効果的です。
家族全員で「水分タイム」を決めて一緒に飲む、食事やおやつごとに飲み物をプラスするなど、家族ぐるみで日々の水分補給をサポートしましょう。
「今日は暑いからいつもより多めに飲もうね」「みんなで水分チェックしてみよう」など、季節や体調に応じた声かけや工夫を取り入れることで、無理なく楽しく続けられます。
小さなお子さんや孫と一緒に水分補給を楽しむ時間を作ったり、飲み物やコップ選びをイベント化するのもおすすめです。
家族みんなで水分補給の習慣を身につけることで、高齢者だけでなく家族全体の健康管理にも役立ちます。
こまめな水分補給と家族ぐるみのサポートで、脱水症や体調不良をしっかり予防しましょう。
特別な状況における水分管理

熱中症や脱水状態を予防するための対策
高齢者は体温調節機能が若い頃よりも衰えているため、夏の猛暑や梅雨時の蒸し暑さ、または急な発熱や体調不良などで熱中症・脱水症のリスクが一気に高まります。
そのため、室内であっても冷房や扇風機を適切に利用し、室温は25〜28度前後、湿度は50〜60%程度を目安に快適な環境を保つことが大切です。
日中は汗をかいていなくても体から水分が失われているため、「のどが渇いた」と感じる前に30分〜1時間ごとにコップ半分〜1杯ずつ水分を摂る習慣をつけましょう。
さらに、外出や散歩、運動の際には必ず飲み物を携帯し、直射日光を避けるために帽子や日傘を活用することも忘れずに。
汗をたくさんかいた時や体調の変化に気付いた時には、水だけでなくスポーツドリンクや経口補水液を取り入れて、電解質(塩分・ミネラル)の補給も意識しましょう。
「まだ大丈夫」と思って油断しないことが、熱中症や脱水症予防の最大のポイントです。
家族や介護者は、日中だけでなく朝晩もこまめな声かけと環境調整を心がけ、高齢者自身が気付かないうちにリスクが高まるのを防ぐことが大切です。
旅行や外出時の水分摂取の注意点
旅行や外出の際は、普段と違う環境や移動による疲れ、トイレへの不安などから、知らず知らずのうちに水分補給が不足しがちです。
移動中でも必ずマイボトルやペットボトルを持ち歩き、こまめに少量ずつ飲むことを心がけましょう。
電車やバス、飛行機の車内や機内はエアコンの影響で空気が乾燥しやすく、のどや皮膚が乾燥しやすくなります。
休憩や乗り継ぎのタイミングごとに水分補給を行いましょう。
特に夏場や汗をかくレジャー、観光地などではスポーツドリンクや経口補水液、塩飴を活用して、電解質もあわせて摂取するとより安心です。
「トイレが心配だから」と水分を控えるのは逆効果です。脱水症や熱中症のリスクが上がるだけでなく、血液が濃くなり血栓症などの別の病気を招くこともあります。
食事の際はスープや果物、ゼリー、プリンなど、水分量の多いものを積極的に選ぶようにしましょう。
体調の変化や発汗の有無を自分だけでなく家族や同行者もチェックし、声を掛け合いながら水分補給を徹底してください。
体調による水分摂取量の調整
発熱や下痢、嘔吐、食欲不振などで体調を崩しているときは、通常よりもさらに多めの水分補給が必要です。
発熱や感染症、炎天下の外出などで発汗が多い場合は、普段より1日300~500ml程度多めに摂取しましょう。
ただし、腎臓や心臓に持病がある方、水分制限の指示がある方は必ず主治医や担当医の指示に従ってください。
「食べられない」「飲み物が受けつけない」時は、ゼリーや果物、ヨーグルト、アイスクリームなど食べやすい形状のものから少しずつ摂るのも良い方法です。
高齢者は「のどが渇かない」「だるくて動きたくない」など自覚症状が出にくい場合もあるため、家族や介護者が体調や尿量・尿色、顔色や意識状態を日々チェックし、必要なら早めに医療機関に相談することが大切です。
水分摂取に関するよくある質問(FAQ)

果物やゼリーは水分補給に適しているか?
果物(スイカ・みかん・キウイ・梨など)やゼリー、プリン、ヨーグルトは、食事からの水分補給にとても有効です。
特に高齢者は「飲み物は苦手」「食欲がわかない」という場合も多いため、こうした食品を食事やおやつで積極的に取り入れると、自然に水分摂取量が増やせます。
ビタミンやミネラル、食物繊維も同時に摂れるので健康維持にも役立ちますが、糖分の摂りすぎやアレルギー、持病に注意して選びましょう。
果物やゼリーだけに頼るのではなく、飲み物も合わせてバランス良く摂取することが理想です。
飲み物の取りすぎのリスクについて
腎臓や心臓の病気で水分制限が必要な場合を除き、通常の健康な高齢者が水分を「取りすぎる」ことによるリスクは多くありません。
しかし、短時間に一気に大量の水分を摂ると、体内の塩分バランスが崩れて「水中毒」と呼ばれる危険な状態になることがあります。
めまいや頭痛、けいれん、吐き気、意識障害などが起こることも。
健康な人でも1時間に1リットル以上を一度に飲むのは避け、1日の必要量を朝から夜まで数回に分けてこまめに摂取しましょう。
医師から摂取量制限が出ている場合は必ず守りましょう。
尿の色から分かる水分不足のサイン
尿の色は日々の水分摂取や体調を知る大切なサインとなります。
理想は薄い黄色~ほぼ無色透明ですが、濃い黄色や茶色っぽい色になっていたり、尿量が減った、においが強い、排尿回数が少ない場合は体が水分不足になっている証拠です。
朝一番の尿は少し色が濃いこともありますが、日中も濃い色が続く場合はすぐに水分補給をしましょう。
また、体調が悪い時や脱水が疑われる時には、早めに医療機関に相談することも大切です。
高齢者は自分で変化に気付きにくいことも多いため、家族や介護者が日々の排尿の様子や体調変化を観察し、適切なタイミングで声かけや受診サポートを行うことが、健康を守るポイントになります。
高齢者の水分摂取に関するQ&A(よくある質問と回答)

Q1. 高齢者はなぜ水分不足になりやすいのでしょうか?
A. 年齢とともに体内の水分量が減少し、「のどの渇き」を感じにくくなります。また、腎機能の低下や慢性疾患、薬の副作用も重なり、水分補給が追いつかず慢性的な脱水状態になりやすいのが特徴です。さらに、食事量の減少や発汗量の変化、夏場や発熱などによる体液の損失も影響します。
Q2. どんな飲み物を優先して飲めばいいですか?
A. 基本は水、麦茶、ほうじ茶、ノンカフェインのお茶など、利尿作用が少なく体にやさしい飲み物がおすすめです。暑い日や体調不良時は、経口補水液やスポーツドリンクを適度に取り入れましょう。コーヒーや紅茶などカフェイン入り飲料は利尿作用があるので摂りすぎに注意し、アルコール類は脱水を進めるので控えましょう。
Q3. 水分摂取はどのタイミングで行うのが理想ですか?
A. 「のどが渇いた」と感じる前に、1日を通してこまめに少量ずつ飲むことが理想です。朝起きた直後、食事の前後、おやつタイム、入浴や運動の前後、就寝前など、生活のさまざまなタイミングを「水分タイム」として取り入れましょう。
Q4. 食事や果物からの水分摂取はどれくらい計算していいですか?
A. 食事や果物、ゼリー、ヨーグルトなどから摂取できる水分は、1日摂取量の約半分(600~1000ml前後)になる場合もあります。ただし、食事量が減るとこの分も減るため、飲み物からの補給も必ず意識しましょう。
Q5. お茶やコーヒーは水分補給に適していますか?
A. お茶(特に麦茶やほうじ茶、ノンカフェイン茶)は日常の水分補給におすすめですが、緑茶やコーヒーはカフェインによる利尿作用があるため、飲みすぎには注意が必要です。カフェインを控えたい方はノンカフェイン飲料を選びましょう。
Q6. 一気飲みや短時間で大量に水分を摂るのは危険ですか?
A. はい。短時間に大量の水分を摂ると、体内の塩分バランスが崩れ「水中毒」と呼ばれる状態になることがあります。めまいや吐き気、けいれん、意識障害のリスクもあるので、1日の必要量を数回に分けてこまめに飲むのが大切です。
Q7. 尿や便の状態から水分不足を見分けることはできますか?
A. 尿が濃い黄色や茶色で、量が少ない・においが強い場合は水分不足のサインです。排尿回数の減少も要注意です。便秘気味になった場合も水分不足が影響していることがあります。
Q8. 水分補給を嫌がる場合、どう対策すればいいですか?
A. 飲みやすい温度や味を工夫したり、好きなカップやストローを使う、ゼリーや果物など食べやすいもので水分を摂るなど、本人の好みに合わせて工夫しましょう。家族や介護者が一緒に飲む時間を設けて楽しい雰囲気にするのも効果的です。
Q9. トイレが近くなるのが心配で水分を控えるのは問題ですか?
A. トイレが心配だからといって水分を控えると、逆に脱水や尿路感染症、便秘のリスクが高まります。夜間のトイレ対策としては、就寝前1〜2時間は水分摂取を控えめにし、日中は十分な量を補給するのがコツです。
Q10. 水分制限がある場合の補給方法は?
A. 腎臓や心臓の疾患で水分制限がある方は、必ず医師の指示を守ってください。少量ずつ回数を分けて、体調や尿量・尿色、体重増減を日々確認しながら摂取しましょう。経口補水液や果物などの水分量も制限対象となる場合があるので注意が必要です。
Q11. 夏場や発熱時、下痢や嘔吐がある時の水分補給の注意点は?
A. 発汗が多い夏場や発熱時、下痢・嘔吐がある時は、通常よりも多めの水分補給が必要です。経口補水液やスポーツドリンクで電解質も補いましょう。症状が長引いたり、水分摂取が困難な場合は早めに医療機関に相談してください。
Q12. 家族や介護者ができる見守りとサポートのコツは?
A. 日々の生活で「水分補給の声かけ」「水分チェック表での管理」「好きな飲み物や食品の提案」などを行い、本人が楽しく継続できる環境づくりを意識しましょう。体調や排尿の様子、顔色や意識の変化もこまめに観察し、早めの対応を心がけてください。
Q13. 高齢者に特におすすめの水分補給のアイデアは?
A. 少量ずつ分けて飲む、ゼリーや果物など「食べて摂る」、好みの温度やフレーバーの飲み物を用意する、かわいいカップやストローを使う、一緒に飲む時間を作る、記録をつけて達成感を楽しむなど、その人らしいスタイルで楽しく継続できる工夫がおすすめです。
Q14. 水分補給の継続が苦手な高齢者に対する励まし方は?
A. 無理強いせず、小さな成功体験や達成感を積み重ねることで継続しやすくなります。「今日はいつもより多く飲めたね」「体調がいいね」と前向きな声かけをし、本人の意欲や喜びを大切にしましょう。家族みんなで取り組むことで習慣化もしやすくなります。
【まとめ】

高齢者の健康維持や生活の質の向上において、水分摂取は欠かせない習慣です。年齢とともに体内の水分量や「のどの渇き」を感じる感覚が低下し、慢性的な水分不足や脱水症が起こりやすくなります。
特に夏場や発熱・下痢など体調を崩した時、旅行や外出時には知らず知らずのうちに水分が不足しがちです。
厚生労働省が推奨する「1日1.2リットル以上」の水分補給を目安に、体重や体調に応じて必要な量をこまめに摂ることが大切です。
飲み物だけでなく、食事や果物、ゼリーなどの食品からも自然に水分を摂り入れる工夫をしましょう。
また、一度にたくさん飲むのではなく、1日を通じて少量ずつ何回にも分けて摂取することが水分補給の基本です。
冷たい飲み物が苦手な方は温かい飲み物に変える、レモンや梅干しで風味を加える、ゼリーやプリンなど食べやすい形状のものを活用するなど、自分に合った方法で続けることがポイントです。
家族や介護者も日々の声かけや記録、環境づくりで水分摂取をサポートし、みんなで楽しく健康習慣を身につけましょう。
尿の色や排尿回数、体調の変化に気を配り、異変があれば早めに医療機関に相談してください。
高齢者のこまめな水分補給は、脱水や熱中症、便秘や尿路感染症の予防だけでなく、健康長寿を守るための「一番身近で手軽な健康対策」です。
家族みんなで水分摂取の習慣化を目指し、元気な毎日を送りましょう。
最後までお読みいただきまして
ありがとうございました。