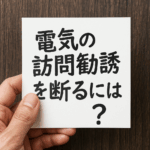儲かっているのに給料が安い会社の理由と、稼げる会社の見極め方

「稼げる会社に入りたい」と思っても、実際には給料に反映されないことも。この記事では、収益構造と給与の関係から本当に稼げる会社を見極めるポイントを紹介します。

「どうせ働くなら、稼げる会社がいい!」って思うのは、誰しも一度は考えたことがあるんじゃないでしょうか。
でも実は、会社が儲かっているからといって、社員が同じようにガッツリ稼げるとは限らないんです。
企業の財務状況が良好でも、その利益がどこに流れていくかは経営のスタンス次第。
この記事では、会社がどうやって儲けていて、そのお金が社員にどのように還元されているのかを見つつ、どんな業界やポジションが“稼げる働き方”につながるのかを、一緒に深掘りしていきましょう!
Contents
会社が黒字でも、社員が裕福とは言えない現実
まず知っておきたいのは、会社の業績がどんなに良くても、その利益が自動的に社員の懐に入ってくるとは限らないということ。
たとえば、多くの企業では、利益を「内部留保」として蓄えたり、「株主への配当」に回したりすることを優先する場合があります。
そうなると、社員の給与や賞与に使われるお金は限られてしまうんですよね。
一方で、「社員にこそしっかり報いるべきだ!」と考えて、利益の一定割合を社員に分配する企業もあります。
この違いは、経営者の哲学や、企業が大事にしているカルチャーによって大きく左右されます。
たとえば、いわゆる「株主第一主義」の企業は、社員の待遇をそこそこにしてでも株価を上げることを優先するケースが多いです。
こういう会社では、もしかしたら社員として働くよりも、投資家として株を買っておいたほうがよっぽど利益が出るなんてことも、現実にはあり得る話です。
つまり、「稼げる会社」と一口に言っても、それが“社員にとって稼げる”のか“株主にとって稼げる”のかを見極める視点が必要なんですね。
稼げる業界を見極めよう:「人の力」か「モノの力」か?
スキルがそのまま収入に直結する業界(コンサル、M&Aなど)
コンサルタントやM&A仲介といった業界は、典型的な「労働集約型ビジネス」です。
これはつまり、社員ひとりひとりのスキルや経験値が、そのまま会社の利益に直結するビジネスモデル。
だからこそ、優秀な人材を確保するために、企業側もかなりの高待遇を用意していたりします。
このような業界では、成果を出せれば1年目から数百万〜数千万円を稼ぐ人も珍しくありません。
特にM&A業界では、1件の成約で何千万というインセンティブがつくことも。
でも、もちろんバラ色な面ばかりじゃなくて、成果が出なければ厳しい評価を受けたり、プレッシャーや精神的な負担も大きかったりするという現実もあります。
高収入=ストレスフリーな環境、というわけではないことは、あらかじめ知っておいた方がいいですね。
商品や技術が稼ぐビジネス(メーカーやブランド系)
これに対して、製造業やブランドビジネスのような「モノ中心」のビジネスでは、企業の収益源は人材よりも製品力やブランドの強さ、知的財産などにあります。たとえば製薬会社なら、新薬の開発成功が数十億円規模の利益を生み出すこともあり、そのための研究費や設備投資が重要なカギを握ります。
こうした企業では、個々の社員の貢献度が直接利益に反映されにくいため、給料も全体的に落ち着いている傾向がありますが、そのぶん雇用の安定性や福利厚生の手厚さが魅力になっているケースもあります。
ただし一概に「メーカー=給料が安い」と決めつけるのは早計です。
業界内でも利益率の高いセグメント(たとえば製薬やハイテク機器など)では、専門性が求められる分、高報酬を得られる可能性も十分にあります。
ポジションの希少性が年収に直結するワケ
どの業界にも共通して言えるのは、「希少なポジションにいる人は稼げる」という法則です。
最たる例が経営層。社長や取締役などは、経営全体の責任を負う重たいポジションですが、そのぶん報酬も破格になることが多いです。
この役職に就ける人は限られているため、会社側も相応の対価を支払わざるを得ません。
また、AIや機械学習などの最先端分野に強いエンジニア、高度なマネジメント能力を持つ営業責任者、会社の方向性を舵取りする経営企画のエースなど、「この人しかできない!」というポジションにいる人もまた、業界を問わず高収入を得やすいです。
ただし、その分プレッシャーやリスクも大きいので、単に「高給だからうらやましい」というだけでは語れないリアルがあります。
総まとめ:「稼げる会社」を見抜く3つの視点
最終的に、「稼げる会社」で働きたいなら、見るべきポイントは大きく3つあります。
ひとつ目は、その会社がどれくらい儲かっているか。
そして、ふたつ目は、その利益が誰に還元されているのか。
社員にきちんと分配される会社もあれば、株主への配当を優先する会社もあります。
三つ目は、自分がその会社のどんなポジションで活躍できるか。
業界やビジネスモデルによって、給与体系や評価基準は大きく変わるので、自分のスキルセットが最大限に活きる場所を選ぶのが重要です。
たとえば、労働集約型の業界であれば、営業力や交渉力を活かして高収入を目指せるし、商品開発系の企業なら、アイデアや技術力で勝負できる可能性があります。
さらには、「この会社、社員より株主が得してるな」と感じたら、もしかしたら働くよりも投資家として関わった方が効率的に稼げるかもしれません。
大事なのは、
「稼げる会社=みんなにとって天国」
という幻想を捨てて、自分にとっての“稼げる形”を見つけること。
そのためには、ビジネスの構造や報酬の分配の仕組みをよく観察し、自分自身の強みを活かせる場所を見極めていきましょう!
最後までお読みいただきまして
ありがとうございました。